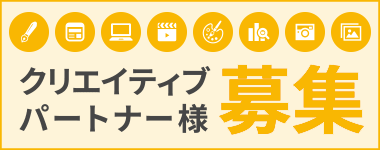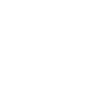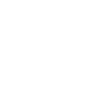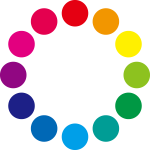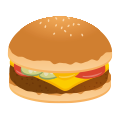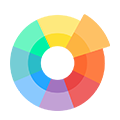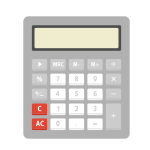プロダクトブランディング
PRODUCT BRANDING
プロダクトブランディングとは?
効果や対象となるものを解説!

「価格競争に左右されない売り方を考えたい」
「商品の魅力を伝えファンを作りたい」
商品やサービスの開発に携わる多くの方は、このように感じているのではないでしょうか。プロダクト(商品)ブランディングは、商品やサービスの価値を高め、消費者からの信頼を獲得するためのマーケティング手法です。本記事では、プロダクトブランディングの基礎知識や効果、取り組むべきこと、大まかな手順について解説します。
プロダクトブランディングとは?

そもそもブランディングとは、企業や商品・サービスにおいて、特定のイメージを浸透させて競合と差別化し、独自の価値を高めるマーケティング活動を指します。
中でもプロダクトブランディングは、商品やサービスに特化したブランディング活動のこと。パッケージデザイン、販路の選択、広告クリエイティブなど、商品が購入されるまでのあらゆるプロセスで独自のブランドコンセプトを貫き、特定のイメージを浸透させることで、消費者との信頼関係を構築します。
プロダクトブランディングに取り組むメリット
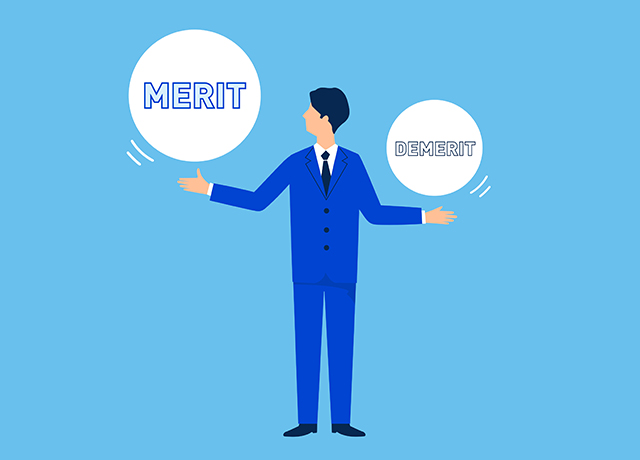
プロダクトブランディングに取り組むことは、以下のような効果につながります。
1商品・サービスに付加価値が付く
プロダクトブランディングによってブランドイメージが浸透すれば、機能や価格ではなく、商品・サービスの付加価値を求めて購入する顧客が現れるでしょう。たとえば、iPhoneを利用しているユーザーの多くは、機能面での価値以上に、「Apple社の商品を持つこと」に満足感を感じています。これは、他社と似たような商品・サービスであっても、「そのブランドであること」が価値になり、その商品を持っていることが安心感や満足感につながるためです。
2ブランドのファンが増える
一度使ってみた商品・サービスがよければ、繰り返し購入してみたくなります。プロダクトブランディングによって、「そのブランドを購入するたびにいつでも同じ価値が得られる」という信頼を蓄積することで、ブランドと消費者が信頼関係で結ばれれば、ブランドのファンになってもらえるでしょう。
3価格競争に巻き込まれない
通常、消費者は、似たような機能を持つ商品であればより安い方を選択します。しかし、プロダクトブランディングが成功し、ブランドそのものが消費者からの信頼を得られれば、価格競争に巻き込まれず、商品価格を維持できるでしょう。また、値上げの必要がある場合も、ブランドへの信頼感が強いファンは変わらず購入し続けるため、プロダクトブランディングの有無は、中長期的な売上に大きな差をつけるでしょう。
プロダクトブランディングで制作するもの
プロダクトブランディングの領域は、消費者が商品・サービスに出会い、比較、購入するまでのあらゆるフェーズに存在します。本章では、商品・サービスにおいて、プロダクトブランディングが影響を与える領域について解説します。
1商品・サービス開発

どんなにパッケージや広告に凝っていても、商品・サービスの質が消費者の求めるレベルに達していなければ、ブランドへの信頼感は生まれません。商品・サービス開発は、プロダクトブランディングのベースになると言えるでしょう。一言で「質を高める」と言っても、原料や製造方法、特許技術や機能、デザインなど、さまざまな方向性がありますが、全てにおいて完璧を目指すことが正解ではありません。商品・サービスの最大の価値をブランドコンセプトに落とし込み、コンセプトに基づいてどんな質を追求すべきか検討してみましょう。
2パッケージ開発

パッケージのデザインや形状は、消費者に商品を認識させ、魅力を伝える重要な要素です。単に奇抜なだけでなく、ブランドのコンセプトが魅力的に伝わり、競合と差別化できるデザインを目指しましょう。たとえば、エナジードリンクの「レッドブル」。缶にデザインされた赤い闘牛のロゴと青い背景は認知度が高く、スポーツイベントなどで赤と青のフラッグを見かければ、レッドブルが協賛していることがひと目でわかります。パッケージでブランディングをはかった商品の成功例と言えるでしょう。
3ロゴマーク

消費者がブランドを認知・識別する重要な要素のひとつがロゴマークです。シンプルで覚えやすく、認識しやすいロゴは商品の質を保証する証として記憶に刻まれ、次に商品を選ぶ時の目印にもなるでしょう。ロゴは浸透することに意味があるため、長く使用することを想定して作成しましょう。また、店頭ツールや看板などにロゴを展開する際、いい加減な使い方をされてしまうと、ブランドイメージに悪影響を与えます。ロゴの取扱い方法を指定するガイドラインを作成しておきましょう。
4キャッチコピー

キャッチコピーは、自社独自のブランドコンセプトを、短く覚えやすい一言で表現したものです。プロダクトブランディングにおけるキャッチコピーは、商品キャッチと住み分けするため、商品の特徴をダイレクトに表したものではなく、ターゲットやシーンを想起させ、ブランドに結びつけるものが良いでしょう。
5広告

商品・サービスの認知向上には、宣伝活動が不可欠です。TVCMのほか、SNS、ブランドサイト、新聞広告、雑誌広告など、多様な媒体から、発信したいターゲットに合わせて媒体を選択しましょう。また、広告のデザインも、ブランドイメージを左右する要素の一つです。ブランドコンセプトに合わせたデザイン・クリエイティブを意識しましょう。
6販売方法
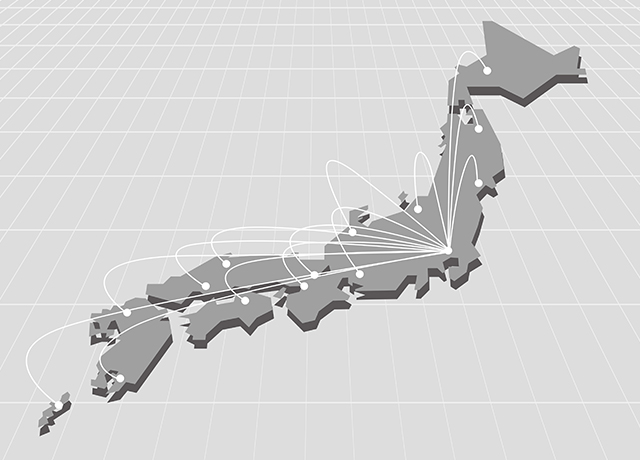
どんなお店でどのように販売するかも、ブランドイメージに関わる重要な要素です。ブランドコンセプトに沿ってターゲットの趣向や行動をイメージし、販売方法を入念に検討しましょう。
プロダクトブランディングの手順

プロダクトブランディングは、一般的に下記の手順で進められます。
| 1 | 市場調査・環境分析 | 「3C分析」、「PEST分析」、「SWOT分析」などのフレームワークを活用し、自社の商品・サービスの強み、弱み、市場環境や競合の動向などを分析します。また、競合分析から自社が強みを発揮できるマーケットを検討し、ターゲットのニーズを抽出します。 |
|---|---|---|
| 2 | ブランドコンセプト開発 | 商品・サービの特徴や新規性、差別化ポイント、ターゲット、競合状況などを踏まえ、「ターゲットにどのようなイメージを持ってもらいたいか」をブランドコンセプトとして明文化します。 |
| 3 | キャッチコピー・デザイン開発 | ブランドコンセプトをキャッチコピーやデザインに落とし込みます。ブランドコンセプトは、「消費者に⚫️⚫️というイメージを浸透させたい」というゴールを定めた際に、「⚫️⚫️」を明文化したもの。キャッチコピーは実際に、「⚫️⚫️」なイメージを浸透させていくための言葉を指しますが、ブランドコンセプトをそのままキャッチコピーとするケースもあります。 |
| 4 | 広告の展開 | プロダクトブランディングでは、商品・サービスの機能を訴求する広告とは別に、ブランド広告を展開します。ブランドのターゲットや商品によっても最適な媒体が異なるため、自社がどんな媒体で広告を打つべきかを慎重に検討しましょう。また、広告の内容やクリエイティブもブランドコンセプトに沿って制作します。広告展開した後は、定期的に効果検証を行いましょう。 |
【まとめ】商品・サービスの差別化が不可欠な時代に、プロダクトブランディングという選択肢を。
モノやサービスがコモディティ化し、価格競争が激化する現代において、商品・サービスを差別化し、市場での価値を保ち続けるために、プロダクトブランディングは必要不可欠です。ブランドコンセプトを開発する際は、自社の商品やサービスの価値はどこにあり、どんな人にその価値が響くのかを考えるところからスタートしましょう。
ブランディングパートナーでは、商品・サービスの価値の掘り起こしから、ブランドコンセプトの設計、キャッチコピー・パッケージの開発、パンフレットやカタログ、ウェブサイトの制作、広告クリエイティブまで、プロダクトブランディングをワンストップでサポートいたします。プロダクトブランディングにお悩みの担当者の方は、お気軽にご相談ください。